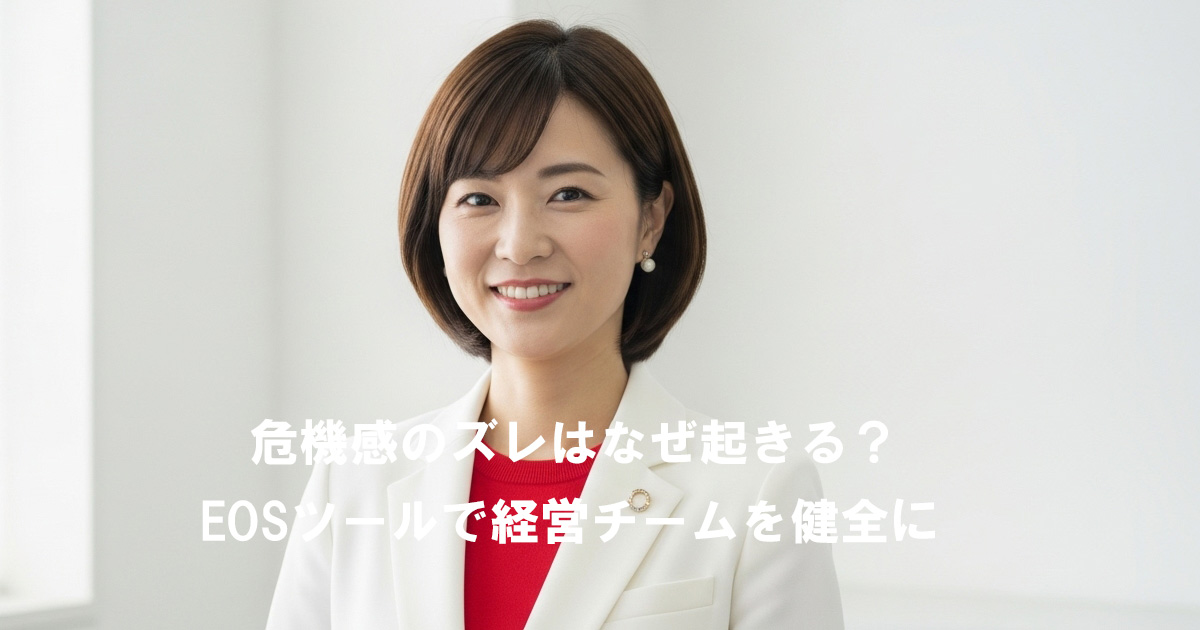「危機感が足りない」「優先順位の感覚が合わない」──経営チームの中で、そんなズレを感じることはありませんか。危機レベルの高い案件が続いているのに、再発防止の行動までつながらない。ヒヤリングで止まり、具体的な対策や基準づくりにまで踏み込めていない。これは、単なる忙しさではなく、チームの健全性が揺らいでいるサインです。
EOSでは、経営者が“やるべきこと”に集中し、組織全体が同じ方向を向くための考え方とツールが整備されています。
アメリカの中小企業で広く導入されているEntrepreneurial Operating System(起業家型組織運営システム)は、ビジョンを明確にし、チームを一体化し、実行を仕組み化するための実践的な経営フレームです。
EOSとは?
経営者やチームが「ビジョンを明確にし、実行を仕組み化する」ための実践的システム。
EOSを導入することで、組織は“やるべきこと”に集中し、健全な意思決定と実行の一体化を実現できます。
この記事では、危機を事前に察知できたはずのサインを見逃し、深掘りが浅いまま再発する組織の構造を見つめ直します。
危機を「感覚」ではなく「基準」でとらえるために──経営チームが再び健全に機能するためのヒントを、EOSの考え方を通して掘り下げていきます。
なぜ危機感のズレが生まれるのか?
感覚のズレは「人」ではなく「構造」の問題
危機感のズレは、誰かの「意識が低い」からではありません。
その多くは、チームの構造的な要因――すなわち、情報の透明性や責任範囲、判断基準の違いに根があります。
危機レベルの定義と行動基準の欠如
特に見落とされがちなのが、「危機レベルの定義」や「行動基準」が共有されていないことです。
誰にとってどの状態が“危機”なのかが曖昧なままでは、
ある人は「まだ大丈夫」と言い、別の人は「もう遅い」と感じる――このズレが意思決定の遅れを生みます。
EOSでは、このようなあいまいさを防ぐために、危機の基準を数字やルールで明文化し、「感覚」ではなく「構造」で合わせることを重視します。
責任範囲と時間軸の違いが“危機感”を分断する
例えば、経営チームの中で同じ出来事を見ても、
営業責任者は「売上への影響」を、経理責任者は「キャッシュフロー」を、現場責任者は「オペレーションの混乱」を危機と捉えます。
それぞれが“自分の責任範囲”で物事を判断しているため、危機への感度や優先順位がずれてしまうのです。
- 情報の受け取り方の違い(数字/感覚/現場肌)
- 責任範囲の違い(営業・管理・現場の視点差)
- 経験の差(危機を経験した量と記憶の差)
- 時間軸の違い(短期的か、四半期・中長期か)
健全性(Healthy)が欠けると“危機を語れないチーム”になる
このようなズレは、単に「温度感が違う」では片づけられません。
危機を“言語化”できていないチームでは、事実を基準に話し合う代わりに、感情や主観で判断してしまうからです。
EOSでは、この状態を「Healthy(健全性)が欠けている」と捉えます。
健全な経営チームとは、危機を避けるチームではなく、危機を早期に共有し、構造的に対処できるチームのこと。
つまり、“危機そのもの”ではなく、“危機への向き合い方”に健全性が現れるのです。
- Open & Honest:問題を隠さず、率直に共有できる
- Team First:個人よりチーム全体の成果を優先できる
- Accountable:責任を自分ごととして引き受ける
危機感のズレは、これらの要素が崩れはじめている“初期症状”といえます。
危機を共通の言語と基準で共有するチームへ
したがって、解決すべきは「危機そのもの」ではなく、危機を共通の言語と基準で認識できるチーム構造をつくること。
この原理を踏まえると、次に求められるのは“視点の転換”です。
危機は“止めるもの”ではなく“見直すチャンス”

危機が発生すると、多くの経営チームは「防ぐ」「抑える」といった防衛的姿勢に陥りがちです。しかし、本来の危機とは“止めるもの”ではなく、“仕組みを見直すチャンス”です。危機は組織のどこかに隠れたサインであり、改善ポイントを照らす貴重な情報源でもあります。
危機を単なる痛みとして扱うのではなく、学びと成長の入口として捉えられるかどうかが、経営チームの成熟度を決めます。ここからは、危機の捉え方を転換したうえで、実際にチームを健全化するための行動へつなげる3つのステップを紹介します。
① 危機ラインを明文化し、“感覚”を揃える
危機感のズレは「誰がどう感じるか」に委ねてしまうと永遠に一致しません。だからこそ、危機の基準を数字や状態で明文化することが重要です。EOSではスコアカードを用い、危機の判断基準を見える化します。
危機ライン設定の例:
- 主要取引先でクレームまたは条件付き対応が発生したら「危機」扱い
- 売上・利益・在庫など重要指標が2週連続で下限を下回ったら即IDS化
- 退職・離職兆候(勤怠・応募数・エンゲージメント低下)を検知したら議題登録
このように「感覚」ではなく「数値や行動」で危機を定義することで、意思決定のスピードと一致率が高まります。
② IDSで“再発防止”まで掘り下げる
危機対応の多くが「ヒヤリングしました」で終わってしまう理由は、議論が深掘りされず、再発防止策まで到達しないからです。EOSのIDS(Identify・Discuss・Solve)は、課題を根本から解決するためのフレームです。
- Identify:事実と根本原因を特定する
- Discuss:責任追及ではなく、仕組みの欠落を議論する
- Solve:担当・期限・再発防止策を明確にし、次週L10で進捗確認
「ヒヤリングしました」で終わらせず、“再発防止まで解決する”ことが重要です。
③ “危機を出せる文化”をつくる
危機の早期発見は、ツールや数値だけでは生まれません。最も重要なのは、メンバーが「この話を出しても大丈夫」と思える文化です。問題を出す人が責められる組織では、危機は隠され、健全性は確実に失われます。
危機を“出せる”文化は、健全性(Healthy)を高め、組織の免疫力を強くします。問題を出すことがチームの成長につながると全員が理解できたとき、危機は初めて組織の財産になります。
まとめ|危機を見つけ、言葉にし、仕組みに変える
危機は、組織の弱点をあぶり出す“悪者”ではありません。
むしろ、今の仕組みを強くするためのサインです。
大切なのは、「なぜ起きたか」よりも「どう活かすか」という姿勢です。
経営チームが健全に機能するためには、危機を恐れるのではなく、
それを早期に“見つけ”“言葉にし”“仕組みに変える”ことが欠かせません。
そのために、まず次の3つを実践してみてください。
- 危機ラインを明文化する:「どこからが危機か」をチーム全員で共有する
- IDSで再発防止まで掘り下げる:ヒヤリングで止めず、Solve(解決)までやり切る
- 危機を出せる文化を育てる:“まずい話こそ価値がある”という合言葉を持つ
危機を出せる組織は、同時に信頼を出せる組織でもあります。
それこそが、EOSが目指す健全で前進し続ける経営チームの姿です。
危機を恐れず、仕組みに、そして構造に変えていく経営チームこそが、変化の時代を生き抜く最強の組織です。
今日のミーティングから、ひとつ「危機を言葉にする」ことから始めてみましょう。
書籍紹介|『TRACTION』は“健全な経営チーム”をつくる実践書
この記事で紹介した「危機ラインの明文化」「IDSで再発防止まで掘り下げる」「危機を出せる文化づくり」は、すべてEOSの中核となる考え方です。その土台を体系的に学べるのが、ジーノ・ウィックマンの『TRACTION』です。
『TRACTION』は、EOS(Entrepreneurial Operating System)を使って
経営チームが“健全に機能する組織”へ変わるための公式ガイドブック。
ビジョンづくり、目標の設定、会議の仕組み化、課題解決、構造の見直しなど、組織運営の要素をシンプルかつ再現性のある形でまとめています。
特に本記事のテーマに関連するポイントとしては、
- L10ミーティング:危機や課題を“率直に話せる”チームをつくる会議フォーマット
- IDSプロセス:再発防止まで掘り下げる課題解決の公式ステップ
- スコアカード:危機を感覚ではなく「数字」でとらえる仕組み
- アカウンタビリティチャート:誤った構造を正し、責任のズレを解消するフレーム
これらのツールはすべて、本記事で触れた「危機を見つけ、言語化し、仕組みに変える」ための基盤として機能します。危機対応や組織の健全性に課題を感じる経営チームにとって、『TRACTION』は必ず役立つ一冊です。
▶『TRACTION』ビジネスの手綱を握りなおす 中小企業のシンプルイノベーション
ジーノ・ウィックマン 著